こんにちは。いつもお世話になっております。青沼隆宏です。
あおぬま通信第131号をお送りします。少し長くなりますが、お付き合いください。
最近、AIや自動化の話題をよく耳にします。たしかに便利ですし、僕もありがたく使っています。
でも、現場を見ている(ちなみに僕自身はお客様に出せるようなモノづくりは出来ません)と「体に情報を入力する」ってやっぱりすごいな、と感じる瞬間が多いんです。
たとえば溶接。職人は、音で判断します。
アークの音が良い時は電圧やトーチを送るスピードが調和している。
逆に音が悪い時は調和が乱れている(残念ながら音の良し悪しは僕には判断できません)。
温度計なんて要らない。耳と手で判断して、体が勝手に動く。これが“熟練”です。

切削もそう。旋盤で鉄を削る音で正しい削り方をしているか判断します。基本的には刃の切れ具合と送りスピードの調和です。早くすれば良い訳でも遅くすれば良い訳でもありません。「丁度よい」があります。それを音で判断します(残念ながらこちらの音の良し悪しも僕には判断できません)。
指で撫でれば、仕上がりがすぐに分かります。
寸法が図面どおりでも、手触りが悪ければ“仕上がりの悪い仕事”。
数値よりも感覚が正確な世界です。
ソフビも同じ。材料の状態、部屋の温度や湿度、時間帯。
違えば、表情が変わります。
それを「失敗」と思う人もいるかもしれないけれど、僕はむしろ“味”だと思う。
人の手でつくるからこその揺らぎ。それが作品を生かしている。
手曲げによる抜き刃づくりも、手の加減がすべてです。
どの程度の強さ・リズムで叩いていくか。その強さとリズムを正確に刻むことが出来るか。
これはもう体が覚えているとしか思えない。刃の高さと曲げ具合によってきっと最適な強さとリズムがあるんだと思います(残念ながら、これも僕には出来ないのであくまでも想像です)。
こういう仕事を見ていると、手仕事って本当にすごい。
手仕事で入力した情報で脳をコントロールしている。
便利な時代になっても、この「体を使うことによる入力」こそが、人間の本領なんだと思います。
人には心と体があります。でも、その二つは別々じゃない。
もし僕が185cmの体格を持っていたら、きっと今と違う人生を歩んでいたでしょう。
体に規定されている以上、体に入る情報(音、重さ、温度、匂い等)が、心のあり方(若しくは脳が仮定する限界)を作っている。
だから僕は、職人のような「体に入力を続けている人」の感覚を信じる人間でありたいと思います。
世の中がどんなに進んでも人が体を持っている以上、手で感じ、耳で聴き、体に色々な入力を続ける。
その作業を失わない限り、人の仕事は拡張できる。
そんなふうに思うこの頃です。
北海道は既に雪が降りました。
どうぞ温かくしてお過ごしください。





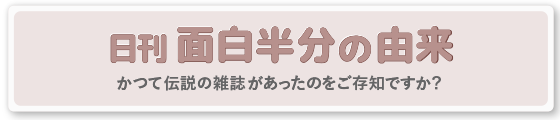


コメント欄
コメント一覧