こんにちは。いつもお世話になります。青沼隆宏です。
あおぬま通信第130号をお送りします。読みづらい部分もあるかもしれませんが、ご容赦ください。
10月に入り、自民党の総裁が交代しました。テレビ等でも大きく報道されていましたが、その直後から株価が急に上がり、円安が進みました。ニュースでは「市場が期待している」と言われています。新しい総裁のもとで財政を拡大し、国の支出を増やす方針が見えてきたということでしょう。

ただ、こうした変化は私たちのような中小製造業にも少なからず影響があります。
円の値段が下がる、いわゆる“円安”になると、輸出をしている企業には追い風ですが、輸入した材料を使用している工場にとっては仕入れが高くつきます。鉄・機械・燃料など、どれも値段が上がりやすくなります。
もちろん、価格を上げてその分を取り返せればいいのですが、実際にはお客様との関係や業界の慣習もあり、すぐに転嫁できるわけではありません。多くの工場では「値上げできないコストアップ」との戦いが続いています(弊社は比較的価格転嫁を行いますが、理由は後ほど)。
最近は「物価が上がっている」「株価が上がっている」と言われても(実際上がっていますが)、現場では景気が良くなっている実感はあまりありません。むしろ、光熱費や人件費の上昇で、経営の足元は以前より厳しくなっているように感じます。

それでも前を向くためには、私たち中小製造業がどう動くかが大切です。
たとえば、
- 原材料やエネルギーの使い方を見直して無駄を減らす。
- 社員が長く働けるように待遇を少しずつでも良くする。
- 「製造業のような、地味だけどなくては困る仕事」をもっと発信していく。
こうした積み重ねが、長く続けられる会社をつくるのだと思います。
最近よく感じるのは、人の採用の難しさです。事務職はリモートや在宅ができるので応募が多いのに、現場の技術職となると応募が極端に減ります。仕事の性質上「現場に来なければできない」ため、どうしても人が集まりにくい。
AIが進化しても、ソフビを成型したり、彩色したり、鉄を削ったり、溶接したり、刃を曲げたりといった仕事は、人の手が欠かせません。こうした仕事を担える人は今後ますます貴重な存在になります。もしかすると近い将来、現場の技術者の給料が事務職(専門職)より高くなる時代が来るかもしれません。それだけ現場の価値が見直されていくと思います。
だからこそ、私たちは「安く請ける」のではなく、「適正な価格で、誇りを持って続けられる仕事」を増やしていかなければなりません。利益をきちんと確保して、社員に還元していく。その循環を止めないことが、工場を未来につなぐ唯一の道だと感じます。
株価や為替の動きはニュースで大きく取り上げられますが、その裏で地域の工場は日々の現場で黙々と支え合っています。どんなに経済が動いても、人が体という実体を持っている以上、最後に社会を支えているのは“現場で実際にモノづくりをする人”です。
これからも、そうした人たちが誇りを持って働ける工場を目指して、一歩ずつ進んでいきたいと思います。
北海道は朝晩の冷え込みが強くなってきました(東京も急に涼しくなってきました)。どうぞ体調にお気をつけてお過ごしください。

函館旅行へ行ってきました。一泊二日だったので「ゆっくり」という感じではありませんでしたが、大沼・赤レンガ・夜景・五稜郭・ホーストレッキング・ラッキーピエロと函館を楽しんできました。仕事抜きで行くのは久しぶりで、楽しめました。赤レンガに運河と函館と小樽は似ていると思いました。そういえば横浜にも赤レンガ倉庫がありました。


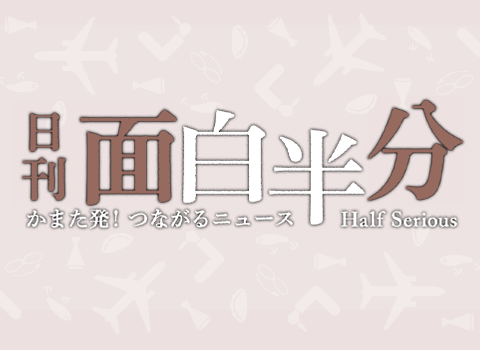


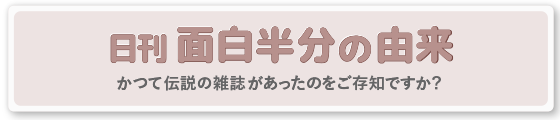


コメント欄
コメント一覧