先日、札幌の展示会に行ってきました。歩いていると、FRP製の支柱が目に入ったんです。最初は「FRPでもパイプ形状のものが作れるんだなぁ」と軽く眺めていたのですが、よく見ると軽くて、腐食にも強くて、なんとなく気になる存在になってきました。
少し進んだ別のブースでは、監視カメラ、風速計、湿度計等のセンサーや通信モジュールのような電子機器を設置した支柱が展示されていました。まったく別ジャンルの製品なんですが、見ていたらつい「この支柱を防雪柵の支柱にして、素材も鉄からFRP製へ変更したら、どうなるんだろう?」と想像してしまいました。
上写真:展示会で見たものと似ている監視カメラとセンサー付きの支柱
もしそれができたら、防雪柵の「支柱」は、ただの構造物ではなくなります。軽量で設置が楽になり、センサーが積雪量や風速を測り、カメラが害獣の侵入を見張り、AIと連動すれば、風速でパネルの角度を自動で変更したり、自動で通報したりする事ができるようになる。ドローンを組み合わせたら、侵入を見張るだけでなく、撃退まで……なんて事もできるかもしれません。防雪柵が、冬だけでなく春夏秋も“働く存在”になったら面白い。
そんなことを考えるようになったのは、実は釣りがきっかけでした。
以前は、魚群探知機といえば湖底の地形が映る程度で、「地形から、多分この辺に魚がいるだろう」と想像で釣りをしていました。まずは目立つルアーを投げてみて、反応がなければ徐々に地味なものに変えていく。魚がいるかいないかも分からないまま、「釣れない=いない」と判断して場所を移動する。そんなスタイルでした。
ところがある日、最新のガーミン製ライブスコープ(前方が見える魚探)を使ってみて、世界が一変しました。湖底の地形だけでなく、泳いでいる魚の姿、自分のルアーに反応している様子までもリアルタイムで映し出される。魚がルアーを追ってきているのに喰いつかない——そんな瞬間が“目で見える”のです。これには驚きました。
上写真:ガーミン製ライブスコープ画面
特に衝撃だったのは、「魚はいる。目の前にルアーを通している。反応している。でも口を使わない魚が、こんなにたくさんいるのか」という事実を“見せつけられた”ことでした。
この体験で、釣り方そのものが変わりました。今ではまず、喰わせ重視の地味なルアーを魚のいるピンポイントに投げて反応を見る。それでダメなら、派手なルアーでリアクションを誘い、それでもダメなら場所を変える。つまり、情報の精度が高まれば、無駄を減らして合理的な選択ができるということです。
この考え方、きっと漁業の現場にも応用できるんじゃないかと思うのです。たとえば、深度500mまで潜れる水中ドローンを使って、ホタテの発育状況をリアルタイムで確認できれば、より適切なタイミングで操業ができるはずです。
いや、もしかしたらそれだけじゃないかもしれません。より正確な情報が手に入ることで、人の頭のスイッチが入る。今までは想像すらしなかったような、まったく新しい漁法や考え方が生まれる可能性だってあると思うんです。
もちろん、そんな未来がすぐ形になるとは思っていません。FRPの加工性、電源や通信の確保、コスト……課題は山積みです。でも、「それ、やってみたら面白いかもね」を想像して、少しずつでもできることから手をつけてみる。そうやって積み重ねていく一歩一歩が、僕たちのモノづくりの出発点なんだと思っています。
鉄で支えてきた地域を、情報でも支えられるようにする。そんな未来を夢見ながら、今月はFRPとAIと釣りの話をお届けしました。





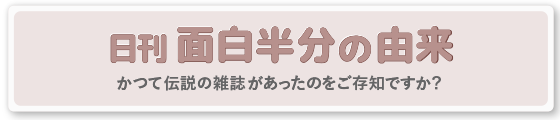


コメント欄
コメント一覧